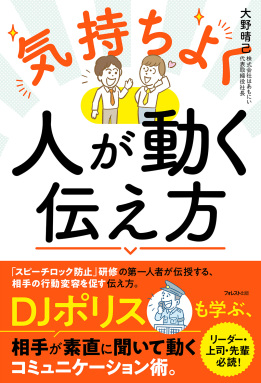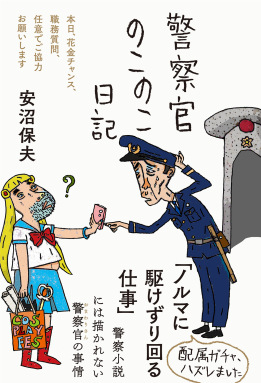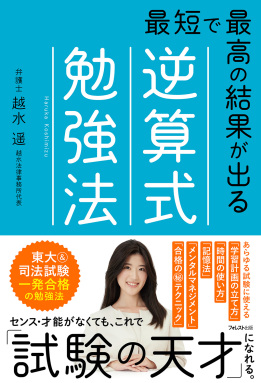著者の関連商品
著者の関連商品
-
「ダークトライアド」という中2心をくすぐる言葉を知ったのは、ネットサーフィンをしていたとき。ダークトライアドを構成するナルシシズム、マキャベリアニズム、サイコパシーを『チェンソーマン』のように悪魔化したキャラクターをつくったら面白そうだな、という思いつきから企画が生まれました。研究者である著者が、専門的で難しい話を、一般向けに噛み砕き、事例を交えながらわかりやすく解説しています。読んでいて気づいたのですが、私はナルシシズム高め、マキャベリアニズム低め、サイコパシー高めのようです。本当の自分や他人を知り、よりよい社会生活やコミュニケーション、キャリアを築くには大切な知識です。

POSTED BYかばを
View Moreナルシシズムの悪魔、マキャベリズムの悪魔、サイコパシーの悪魔…
本書は、心理学において現在進行形で活発に研究が進められている最新テーマの1つ「ダークトライアド」の心理・行動パターンとの関連を一般向けに解説している。
3人の悪魔は、私たちを成功に導き、あるいは破滅させる
ダークトライアドとはナルシシズム、マキャベリズム、サイコパシーの3つのパーソナリティの総称で、しばしば三角形で表現される。
自己中心的で他者操作的、かつ共感性の欠如などが共通した特徴。
セクハラ、パワハラ、裏切り、嘘、マウンティング……私たちは人間関係を通してさまざまな嫌な思いをし、もしかしたらさせているかもしれない。
その根底には、このダークトライアドが潜んでいるのだ。
このように、ダークトライアドは共に力を合わせて営むべき我々人間社会にとっては望ましくないかもしれないが、一方で個人の人生をより豊かにするにはこうした性質も必要になる場合があるという。
これは誰もが持っている邪悪なパーソナリティなのか?
相手や自分の中の“悪魔”を飼いならす方法はあるのか?
さらに、「4人目の悪魔」サディズムとは?
こういう人、身近にいないだろうか?
平気で嘘をつく/自身が「HSP」であると自己呈示する/ネットで誹謗中傷を繰り返す/マウンティングをとる/リーダー的立場につくことが多い/パワハラやモラハラをする/寝取り寝取られ経験が多い/セフレがいる/男女ともに反フェミニズム傾向/第一印象はよかったが……...etc.
あるいは自身の行動に身に覚えはあるだろうか?
こんな人に読んでほしい!
●他人や自分に振り回されて心が疲弊している人(エキセントリックな性格の人が身近にいる人、自分のなかの望ましくない感情を自覚している人、いつも遠慮して損ばかりしていると感じている人)。
●「サイコパス」など、人の心の闇に関心がある心理学好き。
目次
まえがき より豊かな生活を送るために、あえてダークな心を覗き込む
第1章 そもそもダークトライアドとは何か?
第2章 3人の悪魔とその仮面の下
第3章 悪魔合体した一体の悪魔ダークトライアド
第4章 4人目の悪魔?サディズムについて
第5章 他人や自分の悪魔の見抜き方
第6章 悪魔の飼い慣らし方
あとがき 異なった意味で言葉が独り歩きしないために
-
商品内容View More
●『非常識な成功法則』コレクターズ・エディション(書籍)
●『大発見』新装版(書籍)
●『フューチャーマッピング特別セミナー』全3回(セミナー)
・第1回 2025/3/17(月)20:00〜21:30 オンライン開催(アーカイブ配信あり)
・第2回 2025/3/24(月)20:00〜21:30 オンライン開催(アーカイブ配信あり)
・第3回 2025/3/31(月)18:00〜19:30 都内会場・オンライン同時開催(アーカイブ配信あり)
※会場は決定次第、登録されたメールアドレスにお知らせいたします
※アーカイブ映像は、準備が出来次第登録されたメールアドレスにお知らせいたします
特典
●『非常識な成功法則』コレクターズ・エディション(書籍)へのシリアルナンバー刻印
※シリアルナンバーはランダムで刻印
●『非常識な成功法則』コレクターズ・エディション(書籍)への神田 昌典 直筆サイン
※2025/3/31(月)に都内会場でサイン会を実施。参加者のみ直筆サインを行います。
会場は決定次第、登録されたメールアドレスにお知らせいたします
-
どうすれば、こちらの意図どおりに、相手が気持ちよく聞き入れて、動いてくれるか――。これは、部下を持つ全管理職やリーダー、子どもを持つ親にとって重要な問題です。パワハラ、モラハラなど、ハラスメントに対する意識が年々高まってきている時代ならなおさらなことです。そこでおおいに参考になるのが「DJポリス」です。2013年のサッカーW杯出場を決めた当日、渋谷スクランブル交差点に押し寄せた熱狂的なサッカーファンに対して、交差点の指揮車上でマイクを握って安全誘導アナウンスを行なって、全国的に注目を集めたので覚えている人も多いでしょう。「混乱を避け、安全を確保する」ために、あの群衆に対する、あの上手な伝え方には、大きな秘密が隠されています。キーワードは「スピーチロック防止」です。著者の大野さんは、「DJポリス」のマニュアルの修正や加筆、「DJポリス研修」を担当した人物。そんな「スピーチロック防止」研修の第一人者が、相手から反発がなく、望ましい行動にスムーズに導く「伝え方」のコツをわかりやすく解説してくださいました。ビジネスやプライベートにも使える1冊です。

POSTED BY森上
View MoreDJポリスも学ぶ、
パワハラ、モラハラなど、 ハラスメントに対する意識が年々高まってきている昨今、
相手が素直に聞いて動く
コミュニケーション術
多くの上司やチームリーダー、親御さんたちは、
自分が「相手にこうしてほしい」と思うことを
うまく伝えることに四苦八苦しています。
相手にやってほしいこと、
伝えたいこと、言いたいことが、
思いどおりに言えない、伝わらない――。
そのもどかしさは、
個人の心理面はもちろん、
組織や集団におけるマネジメントにおいても
大きなダメージ、損失になるでしょう。
例えば企業であれば、
収益をあげるために必要なノウハウやアドバイスを
部下やチームメンバーに的確に伝えて、
行動してもらわなければ、
その企業はいずれ経営破綻してしまいます。
では、どうすればいいのか?
その答えを本書でお伝えします。
本書の重要キーワードに
「スピーチロック」という言葉があります。
これは、ひと言で言うと、
「相手の行動を制限する言い方」。
つまり、言葉の選び方、伝え方によって、
相手の行動を制限し、心理的にも負荷をかける
「言葉の拘束」をしてしまう可能性があります。
逆に言えば、
「スピーチロック防止」を意識した
言葉選び、伝え方ができれば、
相手からの反発がなく、
相手の行動を制限することもなく、
望ましい行動に導くことができるわけです。
わかりやすい例を挙げると、
2013年6月、
サッカー日本代表がW杯出場を決めた当日、
渋谷スクランブル交差点に押し寄せた
熱狂的なサッカーファンに対して、
交差点の指揮車上でマイクを握って
安全誘導アナウンスを行なった
「DJポリス」の伝え方です。
そのノウハウを
徹底解説したのが本書です。
著者は、
この「DJポリス」のマニュアルの修正や加筆、
「DJポリス研修」を担当した人物。
あのDJポリスのように、
相手から反発がなく、
望ましい行動にスムーズに導く
「伝え方」のコツを
わかりやすくお伝えします。
伝えたいことを
しっかり伝えられずに困っている
多くの上司やチームリーダー、親御さんに
お役立ていただける1冊です。
気になる本書の内容
本書の内容は以下のとおりです。
はじめに
第1章 相手の行動を制限する「スピーチロック」とは?
◆言葉による拘束「スピーチロック」とは?
◎その言葉が、相手の行動と心理を制限している!?
◎「スピーチロック防止」の波は、介護からビジネス現場まで波及
◎典型的な「スピーチロック」の言葉
◎サービス業で広がるスピーチロック防止対策
◆スリーロック(3つの拘束)とは?
◎介護現場に起き得る3種類の拘束
◎悪気がなく、無意識でやってしまう「スピーチロック」というリスク
◆スピーチロックに存在する4つの行動パターン
◎行動、静止、意識、無意識
◎「スピーチロックの4パターン」の具体例
◆なぜスピーチロックは起こるのか?
◎スピーチロックが起きる4つの原因
◎原因① 心理的な原因から起きる
◎原因② 出すべき結果が決まっていると起きやすい
◎原因③ 情報編集の能力によって起きる
◎原因④ 頭と身体の状態が一致していないから起きる
◆DJポリスがやっている「スピーチロック」を排した誘導術
◎群衆に素直に行動してもらうマニュアルに修正
◎スピーチロックを使わないDJポリスの雑踏警備マニュアルの中身
◎人流を促進させて行動してもらう、上手な誘導の言葉
第2章 「スピーチロック」と「ヒューマンエラー」の深い関係
◆ヒューマンエラーとスピーチロックはどのように関係しているのか?
◎どんなにAI技術が進んでも、ヒューマンエラーはなくならない
◎ヒューマンエラーの種類
◎レベル1:3つの不足
◎レベル2:ヒューマンエラー「誤認識」
◎レベル3:ヒューマンエラー「機能低下、意識低下、パニック」
◎レベル4:ヒューマンエラー「個人化、コミュニケーションエラー、集団欠如、思考停止」
◎レベル5:ヒューマンエラー「故意、省略・近道行動」
◎レベル5のヒューマンエラーを引き起こす人のタイプ
◎ヒューマンエラーの境界線
◎「ヒューマンエラー」と「スピーチロック」の密接な関係
◆「スピーチロック」は「ヒューマンエラー」を誘発する
◎言い方、言葉の選び方次第でパワハラになる
◎スピーチロックによって起きたヒューマンエラー&事件
◎「スピーチロック」を甘く見てはいけない
◎ヒューマンエラーを排除、低減することはできる──エラープルーフ化
◎「エラープルーフ化」の5つの原理
◎「責任追及型」から「原因追求型」に転換シフトする
第3章 スピーチロックを引き起こす言葉と対処法
◆相手を精神的に傷つけ、行動を抑制してしまう言葉
◎スピーチロックが起こりやすい曜日、時間帯
◎スピーチロックを引き起こす言葉は5種類
◆スピーチロック防止の一番の対処法「言ってはいけない言葉」を排除
◎「言ってはいけない言葉」を使ってしまう要因
◎「言ってはいけない言葉」を排除する6つの対処法
◎スピーチロックの言葉を言い換えるコツ
◆「言ってはいけない言葉」を排除するときの3つのポイント
◎ポイント1:感情的な言葉をあと回しにする
◎ポイント2:相手が行動するための言葉に言い換える
◎ポイント3:結果予知を盛り込んで話す
◎どうしても、自分の感情が先に出てしまう人へ
◆「あいまいな言葉」は、スピーチロック予備軍になる
◎「また電話します」って、いつ? 「ちゃんとしてね」って、どのような状態?
◎「あいまいな言葉」が使われる3つの原因
◎「あいまいな言葉」を使わない6つのコツ
◆「使い方が間違っている言葉」を知る
◎言葉で、人を「モノ」「道具」扱いしていないか
◎日本語の誤った使い方にご用心
◎「赤ちゃん扱いする言葉」にも気をつけて
◆「マイナス/ネガティブ言葉」を肯定表現、プラスの言葉に言い換える
◎「マイナス/ネガティブな言葉」が口から出てしまう原因
◎「マイナス/ネガティブな言葉」を使わないようにする6つのコツ
◎言い換えの練習
◆「言葉が足りない」を解消する
◎「言葉が足りない」が起こってしまう2つの要因
◎「言葉が足りない」を解消する6つの対処法
第4章 シチュエーション別「言葉」の言い換え
◆時代とともに言葉の使い方も変わる
◎「父兄会」ではなく「保護者会」
◎世代間ギャップが生み出すスピーチロック
◆ジェネレーションギャップを埋めるスピーチロック防止法
◎世代間ギャップがハラスメントを生む時代
◎世代間ギャップを感じる言葉
◎世代間ギャップを埋める対策
◎時には「言わない」という選択肢もある
◆虐待防止につながる言葉の言い換え
◎「高齢者虐待」防止につながる言葉の言い換え
◎「児童虐待」防止につながる言葉の言い換え
◆「ハラスメント」防止につながる言葉の言い換え
◎職場におけるハラスメント発言例
◎「セクハラ」につながる言葉
◎ジェンダーバイアスによる発言も要注意
◎これは指導? セクハラ?
◎「おしゃれ」と「身だしなみ」を混同してはいけない
◆「クレーマー」対策のための言葉
◎「カスハラ」対策も義務化へ
◎「クレーム」「苦情」「リクエスト」の違い
◎クレームの種類(一例)
◎クレーマーのタイプ別の対処法
◎典型的なクレーマーの言葉の一例
◎クレーム防止の極意12カ条
◎典型的な応対「謝罪フレーズ」
◆ビジネスシーン(職場)で防ぐ言葉
◎「存在を認める」大切さ
◎「できる上司」は良い言葉を持っている
◎できる上司が使っている言葉
◆「教えない上司」を「教える上司」に変える
◎ハラスメントを気にしすぎて「教えない上司」が増えている
◎「教えない」ことは、言葉なきスピーチロック
◎教える基本の3つのポイント
◆部下に教えるときの言葉の選び方
◎間違えがちな言い回し
◎部下(後輩)が使うと良い上司(先輩)への言葉
◎上司(先輩)が使うと良い部下(後輩)への言葉
◎脱スピーチロックに求められる「情報編集能力」
◎言いたいことがソフトに伝わる「クッション言葉」
◆職場に潜む「スピーチロック」を回避する
◎職場はスピーチロックだらけ
◎スピーチロックを脱スピーチロックにする言い換え例
◆保護者として知っておきたい「スピーチロック」子育て編
◎親子のラポール形成に効果的な言葉「ほめ言葉」
◎「ほめ言葉」を使いたい3つのタイミング
◎ほめるのが苦手な人の特徴と改善法
◎保育園であった「スピーチロック」事例
◎子どもに「スピーチロック」の言葉を使わないための10のポイント
第5章 「非言語表現」を最大限活用する
◎言語表現と非言語表現の割合
◎非言語表現は7種類
◎非言語表現1:周辺言語──「声の高低」「話の間」など
◎話す内容より影響力がある
◎非言語表現2:表情・アイコンタクト・スマイル
◎マスクをしたまま話すと、これだけ損をする
◎非言語表現で最強の表情筋「眼輪筋」
◎「まばたき」の意外なる影響力
◎コミュニケーションの質も、人生の質も変える「笑顔」のつくり方
◎顔の表情は3種類
◎非言語表現3:身体表現
◎非言語表現4:空間の使い方
◎非言語表現5:色彩
◎非言語表現6:モノによる自己表現
◎非言語表現7:タイム&タイミング
◎非言語によるメッセージを感じる力を育む方法 -
「ノルマに駆けずり回る仕事」View More
警察小説には描かれない
おまわりさんの事情
――配属ガチャ、ハズレました
本書をきっかけに警視庁内で「犯人探し」が始まるかもしれない。私に対する非難や中傷もあるだろう。だが、誰になんといわれようと、本書にあるのはすべて私が実際に体験したことである。
――現場で汗を流す末端の警察官の、よいことも悪いことも含めたリアルな姿を描きたいと思う。
もくじ
まえがき――警察官は警察小説を読まない
第1章 ようこそ警察学校へ
某月某日 オリエンテーション:入校前日の腕相撲
某月某日 幸か、不幸か…:教場と、鬼助教
某月某日 教練はつらいよ:警察学校初ビンタ
某月某日 メリメリ教場:「警察官に頭脳はいらねぇ」
某月某日 拳銃係:コツは〝ぎゅう・ドン〟
某月某日 出世頭:教場内カースト
某月某日 マンキョウ第1号:束の間、デート気分
某月某日 脱落者:次は自分の番なのか?
某月某日 夢や情熱もないままに:警察官を目指したワケ
某月某日 拳銃検定:警察官になる覚悟
某月某日 渋谷駅前交番:現場実習・日勤篇
某月某日 110番は鳴りやまない:現場実習・夜勤篇
某月某日 腰撃ち:現場以外での使用
某月某日 正直者が損をする:「ふぁい」処世術
某月某日 解放感:女子学生が披露したマル秘ネタ
某月某日 涙の卒業式:いい思い出なんてないけれど
第2章 配属ガチャ、ハズレました
某月某日 着任:「おんめぇもそう思わねえか?」
某月某日 交番勤務の1日:日勤篇と夜勤篇
某月某日 花金チャンス:評価は、職質検挙と交通取り締まり件数
某月某日 厳然たるヒエラルキー:内勤と外勤のあいだには
某月某日 パンティ泥棒、侵入:時価、おいくらですか?
某月某日 地獄の慰安旅行:旅館の宴会係が嫌う3つの職業
某月某日 バスタオル女子:駆けつけるゴンゾウ
某月某日 武者震い:機動隊への異動
某月某日 街宣車襲来:機動隊の、ある1日
某月某日 祭り、花火、初詣:雑踏警備の極意
某月某日 金欠疑惑:警察は金絡みトラブルを嫌う
某月某日 自殺:「口外しないように」
某月某日 警察官の恋愛事情:「そうだ、京都行こう」は困ります
某月某日 3・11被災地派遣:「余計なことしちゃったかな」
第3章 事件は☓☓で起きている
某月某日 社会不適合警官:久しぶりの交番勤務
某月某日 万引き処理:「被害届出さなくていいんですか?」
某月某日 職質検挙1件ゲット!:高揚感と安心感
某月某日「留置ってベロリですよ」:留置係の1日
某月某日 ハードモード:「今すぐ☓☓☓やめなさい」
某月某日 「声を聞かせて」:面会の人間ドラマ
某月某日 小さな一家:親分の流儀
某月某日 マウント合戦:留置係は知っている
某月某日 情報の宝庫:スモーカー有利な組織
某月某日 組織犯罪対策課:公用車、不正利用
某月某日 ガサ入れ:重大かつ先送りにできない事項
某月某日 刑事人生最大の事件:事件はどこで起こってる⁉
第4章 さよなら、桜田門
某月某日 内規違反:郷に入っては郷に従え
某月某日 絶対的支配者:反抗的な者は…
某月某日 烙印:「嫌なら辞めればいいんだよな」
某月某日 上司ガチャの悲劇:日記シリーズとの出合い
某月某日 退職:「今だったらまだ引き返せるぞ」
某月某日 再会:たった一人の恩師
あとがき――「パパの今の仕事って何?」
【発行】三五館シンシャ/【発売】フォレスト出版 -
著者の越水遥さんは、東大に現役合格、在学中に司法試験一発合格という方ということもあり、よくまわりから「勉強がお好きなんですね」とか、「もともと地頭がいい、いわゆる天才なんですね」と言われるそうです。その際、越水さんは真っ向から否定し、「勉強はあまり好きではないし、天才でも秀才でもないですが、『試験の天才』ではあると思います」と回答するとのこと。越水さんいわく、「勉強がいくらできても合格できるとは限らない。試験合格に満点はいらない。つまり、試験には頭の良さは不要で、必要なのは対象の試験に対して、徹底的にムダを排除し、ピンポイントで完全攻略できるかどうか」。今回の本で完全公開してくださった、合格から徹底的に逆算した勉強法こそが、一発合格の秘訣だったのです。勉強が好きだろうと嫌いだろうと、得意だろうと不得意だろうと、まったく関係なし。誰でもできることを、具体的にわかりやすく解説してくださいました。私も「学生時代に知りたかった……」と本気で思った次第です。中・高・大の受験生はもちろん、資格試験を目指す社会人にも使える内容になっています。

POSTED BY森上
View Moreムダを完全排除し、ピンポイントで完全攻略!
あなたは、
あらゆる試験に使える、
絶対合格から逆算した最強の勉強法
目標とする資格や志望校の
「過去問」をいつやりますか?
試験日の1~2カ月前に
本番さながらの状況で
手をつける人が多いようです。
それだと、
とても非効率で、
ムダの多い勉強になってしまう――。
そう訴えるのが、
東大&司法試験に現役一発合格を実現した
本書の著者、越水遥さんです。
「過去問」は勉強計画の中で、
とにかく最初に手をつけるべきだと言います。
もちろん、解けなくても全く問題なしとのこと。
なぜか?
過去問は、
誰もが平等に与えられる唯一の教材であり、
その過去問に出ている問題や分野から
すべて逆算して勉強すれば、
最短で合格することができるから。
つまり、
志望する資格や学校の試験問題から
逆算して勉強すれば、
ムダを完全排除し、
ピンポイントで完全攻略することができるのです。
言うのは簡単だけど、
実際にどうすればいいのか?
その具体的な方法を
徹底解説したのが本書です。
「学習計画の立て方」から
「時間の使い方」「記憶法」
「メンタルマネジメント」
「合格のマル秘テクニック」。
に至るまで、
絶対合格から逆算した勉強法を
完全公開しています。
この「逆算式勉強法」は、
地頭や才能は関係ありません。
本書に書かれている内容に沿って
勉強計画を立てて、勉強するだけ。
「天才」にはなれなくても、
「試験の天才」には誰でもなれます。
あなたを「試験の天才」にする
重要エッセンスが詰まった1冊です。
気になる本書の内容
本書の内容は以下のとおりです。
はじめに──合格したいなら、過去問から始めなさい
第1章 勉強を始める前に知っておきたいこと――メンタルマネジメント
◆勉強はいわばゲームです
採点者は何を求めているか?
試験攻略は、「暗記」が10割
勉強もレベルは飛ばせない
長期記憶を短期記憶に変換する方法
◆合格するのに、100点は目指さなくていい
試験勉強の最終目的は何か?
広く浅くの勉強は「逆効果」
◆不安や焦りは、試験に真剣に向き合っている証
その焦る気持ちは、合格への第一歩
勉強の痕跡の「見える化」が最強の不安対策
◆不安撃退ルーティンをつくる
自分だけのルーティンを確立する
ルーティンによる成功体験の積み重ねで効果アップ
◆勉強中は自分がビリ、本番中は自分が1位
やる気がなかなか湧かない人へ
本番で「自分が1位」と思い込む方法
◆そこは、本当に勉強できる環境ですか?
人間はサボる生き物だから、あえて「監視の目」をつくる
勉強スペースを複数持つべき理由
◆勉強に集中できる机の環境づくり
机の上を片付けたくなる心理の真相
机は汚くてもいい
勉強しやすい机の整え方
◆勉強仲間は必要か、不要か
試験が終わるまで孤独になったほうがいい理由
メンタル面でも「友だちと勉強」はマイナス
◆合格するまでのスマホとの付き合い方
スマホに振り回されないシンプルな工夫
◆無駄と思える「学校の授業」を有意義にする「予習」法
無駄か有益かは、使い方次第
無駄と思える要因
授業を有意義にするコツ──予習のすすめ
◆無駄と思える「学校の授業」を有意義にする「復習」法
先生がまとめた要点をフル活用
「ノート暗記」こそ有効な復習方法
◆苦手科目との上手な向き合い方
苦手科目があるのは当たり前
苦手科目は克服する必要がない
◆自分にとっての「得意科目」と決める判断基準
他人と比べて決めるものではない
「得意科目」と呼べる科目がなかったら
得意科目、苦手科目を見極める重要性
◆趣味との上手な向き合い方
趣味は付き合い方次第で、プラスに働く
試験が終わるまで続けていい趣味、我慢したほうがいい趣味
とある趣味を封印したワケ
◆始める前に勉強の目的を意識しよう
勉強で力を発揮できる目的設定とは?
勉強の目的は、俗っぽいくらいがちょうどいい
◆最初は質より量
質を追求しすぎる弊害
最初から完全理解を目指さない
◆試験勉強にスタートダッシュはない
試験勉強は長距離マラソン
試験勉強はフライングOK
第2章 最短で最高の結果が出る「学習計画」の立て方――逆算式勉強法の基本
◆逆算式勉強法とは何か?
「勉強ができる人間」になれても、合格できるとは限らない
目標を決めるコツ
将来のビジョンに合った大学を見つける方法
◆「逆算式勉強法」の3つのポイント
ポイント1 過去問をとりあえず1年分解いてみる
ポイント2 すごく大雑把な計画を立てる
ポイント3 勉強時間を記録する
◆【ポイント1】過去問をとりあえず1年分解いてみる
最初は「詳細分析」は不要、意識すべきポイントは?
◆【ポイント2】すごく大雑把な計画を立てる
なぜがっちりと計画をつくってはいけないのか?
「大雑把な計画の立て方」のポイント
あえて無茶な計画を立てる
◆【ポイント3】勉強時間を記録する
記録を取ることの重要性
勉強時間の記録で、自分のクセがわかる
◆参考書&問題集は、「半逆算式」で活用する
半逆算式が最も効率的
問題集をやる意味
◆合格率を上げる「参考書」の使い方
知識すべてを参考書に一本化する──ノートとの違い
参考書にマーカーを引くタイミング
参考書は最低でも3周する
◆合格率を上げる「問題集」の使い方
問題集もまず1周やって、最低3周はやる
間違った理由は問題集に書き込む
◆「問題集」を選ぶポイント
自分に「合う・合わない」が判断基準
問題集は実物を必ず確認
第3章 過去問で傾向とパターンをつかむ方法――無駄にしないための過去問活用術
◆過去問を早めにやってしまうのは、もったいない?
そんなにギリギリにやって、未勉強の箇所があったらどうするの?
過去問は唯一の「平等に与えられる教材」
◆いつ過去問をやるべきか
いつ始めて、どれくらいやればいい?
過去問3年分やることで見えてくるもの
◆過去問を解くにあたっての心構え
模試と過去問、どっちが重要
過去問を最大限に生かす使い方
過去問は、緊迫感を持って本気で取り組む
◆志望校・志望資格の過去3年分でわかること
1年分でわかること、3年分でわかること
足りないのは、時間か、知識か
◆出題傾向とパターンのつかみ方
「どの分野がいつ出たのか」をメモする
出題傾向やパターンの把握は「チート」級
◆つかんだ出題傾向とパターンを活用する方法――ノート術
「過去問まとめノート」で出題者の視点を「見える化」する
過去問から出題者の意図を汲み取る
◆志望校以外の学校の過去問は必要か
ノータッチが原則
第1志望以外の過去問の使い方
◆「模試」との上手な付き合い方
模試の結果が悪かったときの向き合い方
模試のメリット
模試はどれくらい受ければいい?
第4章 絶対合格にコミットする「時間」の使い方
◆ストップウォッチ学習法――自信と効率化の両立
ストップウォッチで時間を正確に計測する効用
3時間勉強しても集中できるのは2時間30分
自分の集中力や1日のスケジュールの限界を知る
◆やっぱり「早起きは三文の徳」
記憶力が高まる時間帯
夜に集中できないときは、無理せず早めに寝る
朝ご飯を食べるまでが勝負の時間
最大のパフォーマンスを出すために、必要な睡眠時間
◆朝起きてから10分でやるべきこと
脳の試運転に合った勉強
今一番やらなければいけないことを日替わりでやる
◆休憩を入れるベストタイミング
科学的根拠に基づいたタイミング
休憩時間のSNS閲覧は危ない
◆休憩時間は終わりを決める
休憩時間の設定法
休憩時間の目安と区切るコツ──ストップウォッチの活用
◆効率のいい休憩時間の過ごし方
おすすめは、明確な区切りがあるもの
受験生が絶対に我慢すべきもの
◆仮眠は取っていい!?
昼食後20分間の仮眠は効果的
「パワーナップ」で勉強効率を上げる
◆なぜ「ルーティン化」は大切なのか?
脳に癖をつける
集中力は才能ではなく、訓練で身につく
◆「集中できない時間」を知る
自分の「集中できない時間」を把握する
集中できない時間の使い方
◆寝る前の「集中できない時間帯」にやるべきこと
暗記もの、数学はNG、おすすめは読み物系
寝る前に絶対やってはいけないこと
◆「宙づりの時間」をつくらない
「宙づりの時間」をなくすコツ
ゴールを明確にすることの重要性
「宙づりの時間」と「スキマ時間」の違い
◆「何もやりたくない日」の時間の使い方
強制的に自分を追い込むコツ
やることは「模擬試験」一択
◆通勤・通学時間に期待しない
通勤・通学時間を過大評価していない?
通勤・通学時間の有効な活用法
◆「時間が経つのを待つ」勉強にしない
時間にこだわりすぎるデメリット
「○時までやる」ではなく、ストップウォッチで計る効用
◆苦手科目に対する勉強時間対策
苦手科目に費やす時間を決めておく
「伸びしろのある科目」に時間を注ぎ込む
◆試験までの残り時間がないときにやるべきこと
応用は捨てる
基礎に時間とコストを全振りする
第5章 超効率的記憶法
◆勉強はなぜつまらないのか?
集中力や記憶力は、興味関心の度合いで変わる
勉強を実生活の楽しさと関連付ける
◆試験勉強は、暗記が10割
試験勉強の合格に「頭のよさ」は不要
試験は暗記ですべて対応できる
◆マークシート式と記述式は、対策が違うのか?
対策は異なるが……
マークシート式と記述式の対策
◆勉強において「理解」は不要?
全体を見ないと、部分はわからない
暗記すれば自然と理解できる
◆伏線は置いていけ
伏線で立ち止まらず、前に進め
まじめな人ほど伏線の罠にはまる
◆小学生に説明できますか?
自分の理解度がわかるバロメーター
どうやって小学生に説明するか
◆見ているだけでは覚えられない
「勉強したつもり」で終わっていないか?
暗記の必勝法は「関連付け」
◆関連付けの簡単な方法
「辞書」を活用して関連付ける
英語でも辞書の活用は有効
「場所」と関連付ける
嘘でもいいので、自分の好きなものと関連付ける
◆暗記は「覚えてから進む」を徹底する
少しずつ記憶を追加する
暗唱は、次に進むための「呪文」
◆五感活用記憶術
五感の記憶と関連付ける
「書いて覚える」ときの注意点
暗記の必須アイテム「ボールペン」
◆ノートに書くとき、カラフルはNG
基本は黒1色
色分けするなら2色まで
◆お絵描き記憶術
文字のみの記憶の限界をビジュアルでカバーする
◆単語帳はつくるな
「点」で覚えるのではなく、「面」で覚える
◆一流の作詞家になってみよう
脳科学が証明する、歌で覚える効用
◆寝ながら覚える、「夢の中勉強法」
夜に暗記できないときの切り札
◆覚えられないところは、とにかく「見える化」
「セルフリマインド」で接触回数を増やす
◆前日覚えたことは翌朝に絶対復習
暗記したことを定着させる秘策
復習のタイミングは朝がベスト
◆持ち歩く参考書は1つに決める
できる限り、選択の迷いをなくす
◆一発合格者がやっている「付箋」活用術
情報追加、補足の必須アイテム
◆エピソード記憶の効力
単語やビジュアル以上の効果
◆「覚える→解く」の繰り返し
暗記を深めるには「解く」こと
おわりに――これから受験を迎えるあなたへ